めねでー◯
噛み砕くと⬇️
釘4本+水1ℓ+クエン酸4g
1. 鉄の溶解(クエン酸による酸洗い)
クエン酸は酸性を示すため、金属の鉄(\text{Fe})を酸化して溶解させ、二価鉄イオン(\text{Fe}^{2+})を生成します。この反応は、空気中の酸素がなくても進行し、水素ガスが発生します。
\text{Fe} (\text{s}) + \text{H}_2\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_7 (\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}^{2+} (\text{aq}) + \text{H}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^- (\text{aq}) + \text{H}^+ (\text{aq})
(クエン酸は多価の酸なので、厳密には複数のプロトンを放出します。)
より簡潔に、クエン酸が酸として働く一般的な反応式を示すと、
\text{Fe} (\text{s}) + 2\text{H}^+ (\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}^{2+} (\text{aq}) + \text{H}_2 (\text{g})
この結果、水溶液は緑色を呈する二価鉄イオンの色になります。
2. クエン酸鉄錯体の形成(キレート化)
生成した二価鉄イオン(\text{Fe}^{2+})や、もし溶液中に三価鉄イオン(\text{Fe}^{3+})が存在する場合(例えば、元々鉄が錆びていた場合や、空気中の酸素で酸化された場合)、これらはクエン酸と安定な錯体を形成します。これを「キレート化」と呼びます。
クエン酸は、複数のカルボキシル基(-\text{COOH})と水酸基(-\text{OH})を持つため、これらの酸素原子が鉄イオンと結合し、安定な環状構造(キレート環)を形成します。
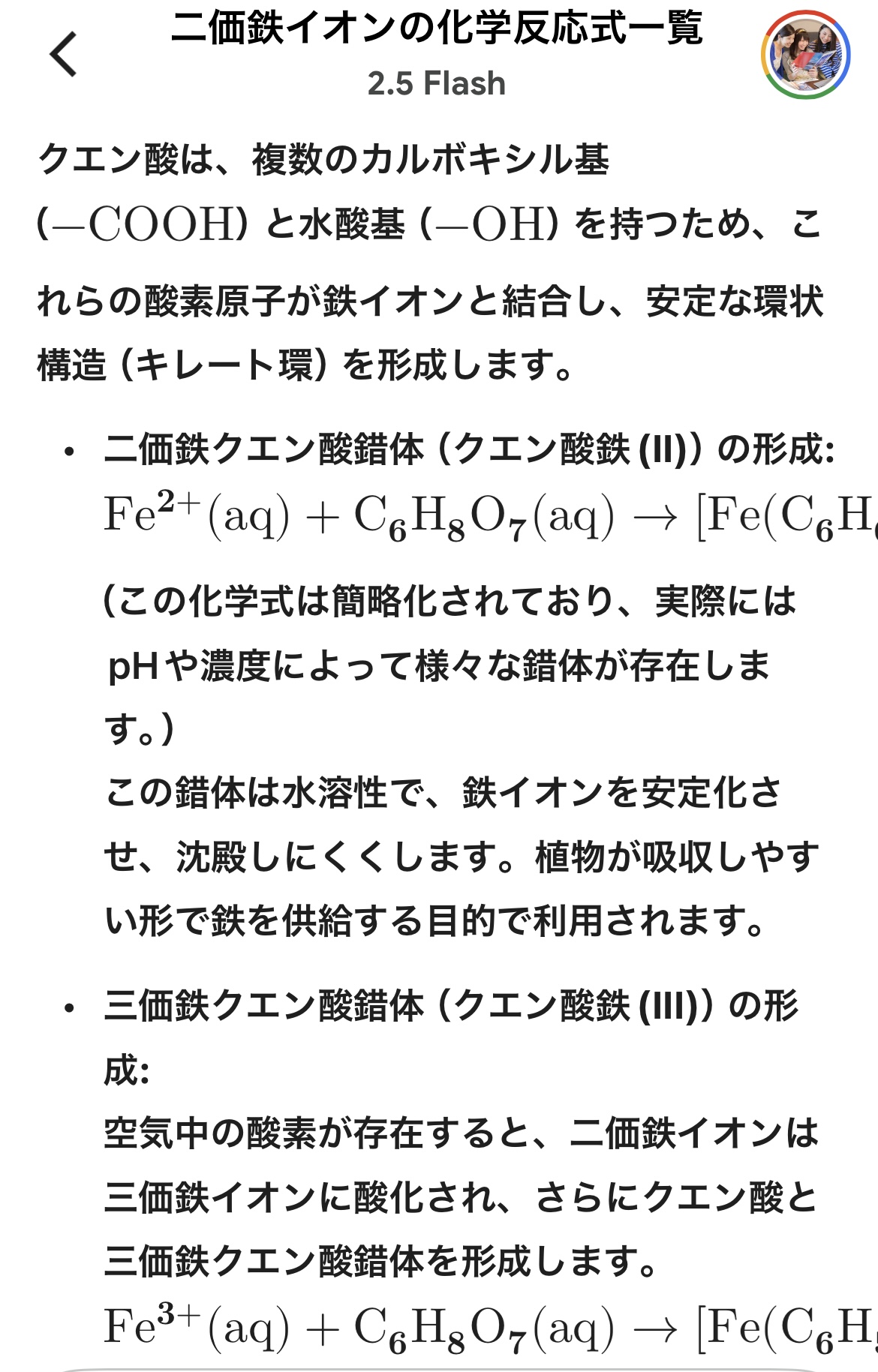 Screenshot
Screenshot* 二価鉄クエン酸錯体(クエン酸鉄(II))の形成:
\text{Fe}^{2+} (\text{aq}) + \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 (\text{aq}) \rightarrow [\text{Fe}(\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_7)] (\text{aq}) + 2\text{H}^+ (\text{aq})
(この化学式は簡略化されており、実際にはpHや濃度によって様々な錯体が存在します。)
この錯体は水溶性で、鉄イオンを安定化させ、沈殿しにくくします。植物が吸収しやすい形で鉄を供給する目的で利用されます。
* 三価鉄クエン酸錯体(クエン酸鉄(III))の形成:
空気中の酸素が存在すると、二価鉄イオンは三価鉄イオンに酸化され、さらにクエン酸と三価鉄クエン酸錯体を形成します。
\text{Fe}^{3+} (\text{aq}) + \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 (\text{aq}) \rightarrow [\text{Fe}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)] (\text{aq}) + 3\text{H}^+ (\text{aq})
(これも簡略化された表記です。)
クエン酸鉄(III)アンモニウムは、サイアノタイプの感光液として使われることがあります。
3. サビ取りにおける役割
鉄のサビ(主に酸化鉄)は水に溶けにくいですが、クエン酸水溶液に入れるとサビが除去されることがあります。これは、クエン酸がサビの主成分である酸化鉄を溶解させ、鉄イオンとして溶液中に取り込む(キレート化する)ためです。
\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 6\text{H}^+ (\text{aq}) \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} (\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O} (\text{l})
(酸化鉄が酸によって溶解し、三価鉄イオンが生じる)
さらに、生じた三価鉄イオンはクエン酸と安定な錯体を形成することで、鉄が再び沈殿してサビに戻るのを防ぎます。
まとめ
鉄、クエン酸、水が共存する系では、以下の主要な反応が起こります。
* 金属鉄の溶解: クエン酸の酸性により、金属鉄が二価鉄イオンに変化し、水素ガスが発生します。
* クエン酸鉄錯体の形成: 溶解した二価鉄イオンや、既存の三価鉄イオンがクエン酸とキレート結合し、水溶性で安定な錯体を形成します。
* サビの除去: クエン酸が酸化鉄を溶解させ、生じた鉄イオンを安定な錯体として保持します。
これらの反応は、クエン酸が鉄イオンを「捕まえて離さない」というキレート効果に大きく依存しています。









