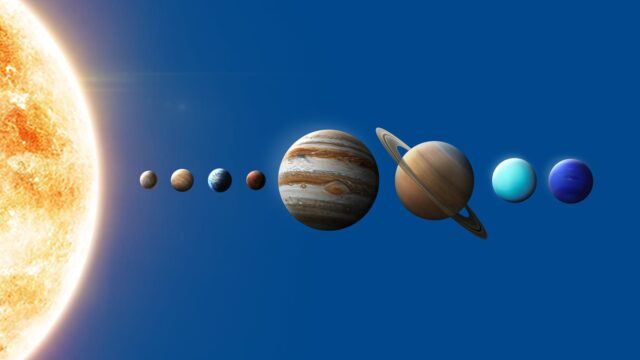AIフィクション⬇️
消えた光、残された人々
2025年7月7日、沖縄・北谷の夕暮れはいつもと変わらなかった。観光客で賑わうビーチには、沈む夕日が黄金色の光を投げかけ、潮風が心地よく肌を撫でる。しかし、この平穏な時間が、突如として音を立てて崩れ去るとは、誰も想像だにしなかった。
午後7時過ぎ、空に最初に異変が起きた。これまで見たこともないような、淡い緑色のオーロラが、南の空にぼんやりと現れたのだ。まるで地球全体を包み込むかのように、それはゆっくりと広がり、人々はスマートフォンを取り出し、その幻想的な光景を撮影し始めた。
そして、その瞬間、すべての光が消えた。
街灯、ビルのネオン、車のヘッドライト、そして手の中のスマートフォンの画面まで。一斉に、何の前触れもなく、世界は絶対的な闇に包まれた。最初に訪れたのは、信じられないという困惑の沈黙だった。次に、あちこちから人々の驚きと恐怖の叫びが上がる。
「停電だ!」「ブレーカーが落ちたのか?」
しかし、それは単なる停電ではなかった。どんなにスイッチを操作しても、どんなにプラグを差し込み直しても、電気が戻る気配は一切ない。スマートフォンはただの黒い板と化し、自動車は路上で機能を停止した。世界中の発電所が、一斉に、その機能を失ったのだ。後に「グローバル・シャットダウン」と呼ばれることになるこの現象は、地球規模で発生し、電力を必要とするあらゆる文明の基盤を一瞬で打ち砕いた。
北谷のコンビニエンスストアでアルバイトをしていた大学生の健太は、突然の闇に包まれ、反射的にレジの奥に身を潜めた。店内の客たちもパニックに陥り、阿鼻叫喚が響き渡る。やがて、わずかな落ち着きを取り戻した人々は、恐る恐る店の外へと出て行った。外は、星空だけが唯一の光源だった。
通信手段も失われた世界で、情報は錯綜した。停電だという者、攻撃されたという者。しかし、数日も経たないうちに、状況の深刻さが明らかになった。ラジオもテレビも機能せず、唯一の連絡手段は、人から人へと伝えられる口伝だけだった。ガソリンスタンドも動かず、車は動かせない。水も、ポンプが動かなければ供給が止まる。食料品店からはすぐに食料が消え、人々は飢えと喉の渇きに苦しんだ。
最初の数週間は、地獄のような混乱だった。略奪が横行し、人々は生き残るために必死だった。しかし、やがて、人間の底力が試される時が来た。電気のない世界で、どのように生きるか。
健太は、近所に住む年配の漁師、慎重(しげゆき)さんと出会った。慎重さんは、電気がなかった時代を生きてきた人物だった。彼は健太に、火の起こし方、魚の捌き方、そして昔ながらの知識を教えてくれた。慎重さんの家には、太陽光で充電する懐中電灯が一つだけあったが、それは本当に必要な時以外は使われなかった。
北谷の住民たちは、少しずつ集落を形成し始めた。海岸では、火を囲んで夜の闇を照らし、共に漁に出て、共同で食料を分け合った。医療施設は機能停止したが、ハーブや伝統的な治療法を知る人々が重宝された。電気で動いていた娯楽はすべてなくなり、人々は歌を歌い、物語を語り合った。
数ヶ月が経った頃、世界は大きく変貌していた。大都市はゴーストタウンと化し、人々は地方へと散らばっていった。電気の恩恵を受けていた便利な生活は失われたが、その代わりに、人々はより深く、互いに繋がり始めた。
健太は、今では慎重さんのもとで、漁師として暮らしている。彼はもうスマートフォンを恋しがることはない。満点の星空の下、燃え盛る焚き火の炎を見つめながら、健太は思う。電気のある世界は便利だった。だが、この、光が消えた世界で、自分たちは本当に大切なものを見つけられたのではないかと。人との繋がり、自然との共生、そして、生きるための知恵。
ある夜、健太は慎重さんに尋ねた。「電気は、もう二度と戻らないんでしょうか?」
慎重さんは、静かに首を横に振った。「それは誰にも分からん。しかしな、健太。もし戻ったとしても、我々はもう、あの頃のようにはならんじゃろう。この闇が、本当に大切なものを教えてくれたんじゃからな」
北谷の夜空には、以前と変わらず星々が輝いている。しかし、その輝きは、以前よりもずっと、意味深く感じられた。人々は、消えた光の代わりに、心の中に新しい光を見つけていたのだ。それは、困難を乗り越え、互いを支え合う、人間の尊い光だった。