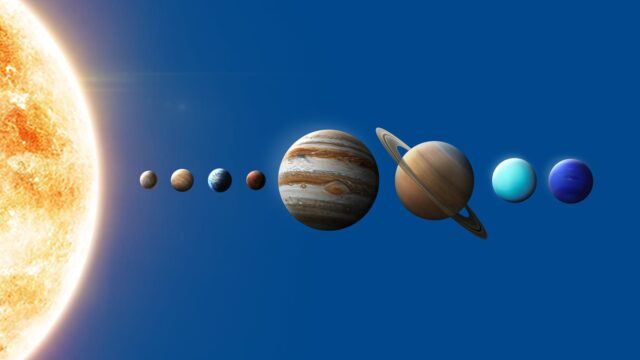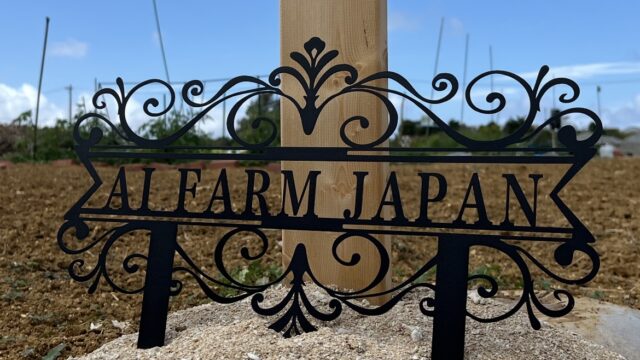スナップエンドウの栽培における収益性についてですね。いくつかの情報源から、その可能性とポイントをまとめます。
1. 収益性の見込み
スナップエンドウは、工夫次第で高い収益が期待できる品目とされています。
* 利益率30%超も可能: ある農家の事例では、1a(100平方メートル)あたり約70kgの収量で、売上22,050円、支出13,820円、収支プラス8,230円、利益率37%を達成しています。反収(1aあたりの収量)をさらに上げられれば、利益も伸びるとのことです。
* 長期出荷と単価安定: スナップエンドウは比較的収穫期間が長く、特にハウス栽培で長期どりを行うことで、安定した収益が見込めます。また、年末年始など需要が高まる時期に高値で販売することも可能です。さやえんどうに比べて価格変動が小さい傾向にあるため、経営が安定しやすいという利点もあります。
* 労力負担の軽減: 他の作物(例:トマトやいちご)に比べて、生産と出荷の労力が比較的かからないことも、高齢の生産者や新規就農者にとって魅力的な点です。
2. 収益向上に向けたポイント
スナップエンドウで収益を上げるためには、以下の点が重要になります。
* 反収の向上: 1aあたりの収穫量を増やすことが最も直接的な収益向上につながります。
* 仕立て技術の向上: 親づるだけでなく、子づるや孫づるからも収穫する「追いかけ取り栽培」に取り組むことで、10aあたり3.0トンまで収穫量を倍増させた事例もあります。
* 施設化・ハウス栽培: 無加温ハウスでの越冬二季どり栽培や、間口6mのハウスで4畝配列し、1mあたり枝数を増やすことで、商品収量約300kg/aを可能にする技術が紹介されています。
販売戦略
* 時期をずらした販売: 市場に出回る量が少ない時期(例:年末年始)に収穫・出荷することで、高単価での販売が期待できます。
* 直販・ECサイトの活用: メルカリなどのECサイトや直販で、独自の価格設定で販売することも可能です。ある農家では、A品850円/500g、B品700円/500g(送料込み)で販売した実績があります。
栽培管理
* 土壌の管理: スナップエンドウは酸性土壌に弱いため、苦土石灰をまいてpHを6.0〜7.0に調整することが重要です。
* 連作障害対策: 連作を避け、3〜4年間マメ科植物を栽培していない土地を選ぶか、土壌消毒を徹底します。
* 水はけの改善: 畝を高くするなどして、水はけの良い土壌を維持することが病害虫対策にもつながります。
3. 市場価格の動向
スナップエンドウの市場価格は、時期や地域によって変動しますが、概ね以下の傾向が見られます。
* キログラム単価: 東京中央卸売市場では、3月1,113円、4月1,237円、5月1,200円、6月657円、7月717円(いずれも平均単価)といった価格が報告されています。
* 年末年始の需要: 11月から12月にかけては、需要が高まる時期に単価が上昇する傾向があります。
* 地域差: 市場や販売ルートによって価格は異なります。例えば、産直サイトや農家直送では、キログラムあたり1,000円を超える価格で販売されているケースも見られます。
スナップエンドウは、栽培技術や販売戦略を工夫することで、安定した収益を期待できる魅力的な作物と言えるでしょう。